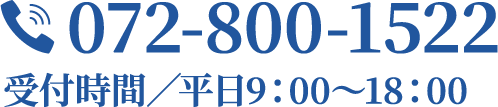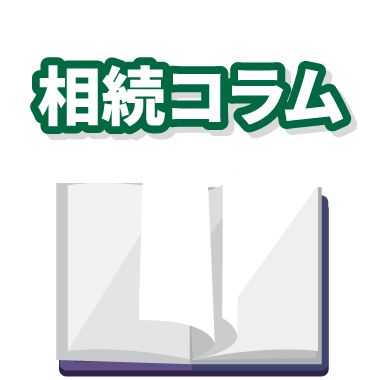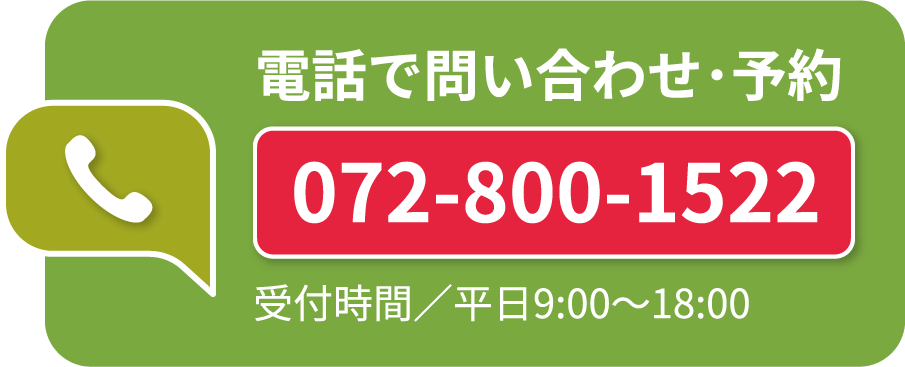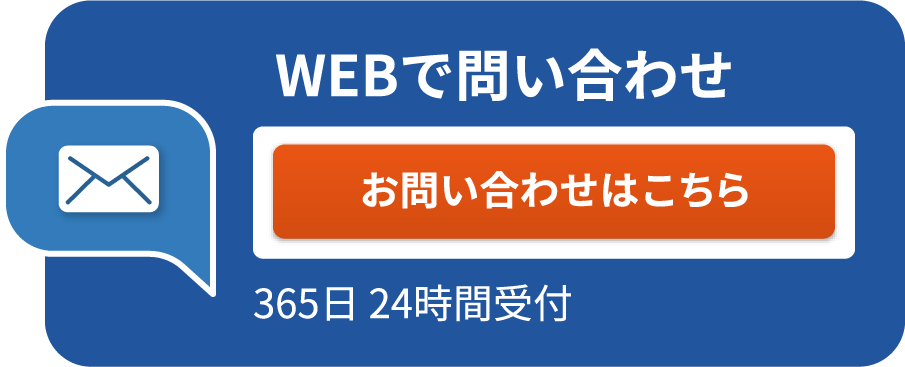ご事情を丁寧にお伺いし、現在お抱えの問題について最適な解決策をご提案いたします。
財産管理委任契約

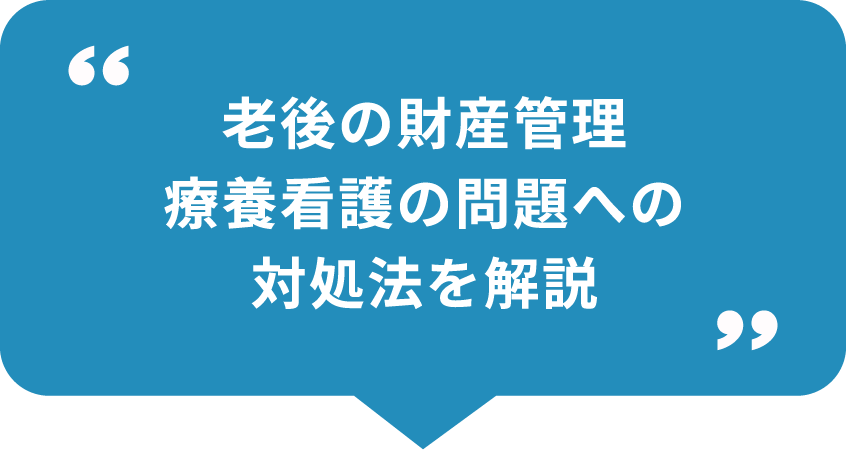
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約は、身体の自由が衰えた時などに「財産管理」や、介護サービスの契約や、病院・介護施設入所の手続きなど「療養看護」のサポートを依頼する契約です。
例えば、外出が難しくなった際の、収益不動産の家賃管理、水道光熱費・税金の支払い、医療や介護などの福祉サービスの利用契約の締結といった適切な療養看護の環境を手配するためのサポートを受けることができます。
なお、財産管理委任契約は口頭の約束だけでも成立します。
しかし、後日委任者と受任者の間でトラブルとならないよう、契約書を作成しておくと安心です。
契約書を公証役場で公正証書の形で作成することがあります。
公証人は元裁判官や元検察官など法律の専門家であり、法的に有効で信頼性の高い書面を作成してもらうことができます。
老後の財産管理方法
老後の身体の衰え、認知症などの判断能力の低下などにより、日常生活を送るうえでの不安を解消するためのサポートは、財産管理委任契約以外にも方法もあります。
どのサポートが自分の希望に合うのか、今一度比較し検討してみましょう。
任意後見制度
判断能力が衰える前に、財産管理や療養看護について信頼できる人を任意後見人として選び、委任しておく制度です。
制度の利用にあたり、公証役場で任意後見契約書の作成が必要です。
本人の判断能力が衰えた時に、任意後見人は家庭裁判所に任意後見契約に基づく事務内容を監督する「任意後見監督人」を選任してもらうための手続きを取ります。
任意後見監督人選任により、任意後見契約の効力が発生します。
あらかじめ委任された事務の内容について、家庭裁判所の監督を受けるため、適切な財産管理・療養看護が期待できます。
財産管理委任契約との違いは、次の通りです。
| 違い | 財産管理委任契約 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 委任内容 | 財産管理・療養看護 | |
| 契約方式 | 当事者の合意だけで成立 | 公証役場で任意後見契約公正証書の作成が必要 |
| 開始時期 | 判断能力の低下前から利用可能 | 判断能力の低下後に利用可能 |
| 管理監督 | 財産管理事務の監督者がいない | 家庭裁判所で選任される任意後見監督人 による後見事務の管理があり安心 |
法定後見制度
本人の判断能力が低下した際に、家族などが家庭裁判所に申立て手続きをおこない、成年後見人などの本人をサポートする人を選んでもらう制度です。
本人の判断能力の低下の程度によって、「成年後見(判断能力がない)」「保佐(判断能力が著しく不十分)」「補助(判断能力が不十分)」の3種類に分かれています。
本人の自己決定の尊重を基本としているため、それぞれの判断能力の程度により、後見人などが本人に代わってできること(権限の範囲)は異なります。
任意後見契約との違いは、財産管理をおこなう後見人などの選任は家庭裁判所がおこなう点にあります。
民事信託(家族信託)
家族に財産管理を任せる信託契約です。
契約により委任開始時期を当事者で自由に決めることができ、判断能力が衰える前からでも利用することができます。
但し、財産管理委任契約とは異なり、療養看護や身上監護を任せることはできません。
| 違い | 財産管理委任契約 | 民事信託(家族信託) |
|---|---|---|
| 委任内容 | 財産管理・療養看護 | 財産管理 |
| 開始時期 | 判断能力が低下する前から利用可能 | |
財産管理委任契約のメリット・デメリット
財産管理、療養看護のサポートを受けるにあたり、財産管理契約利用のメリット・デメリットは次の通りです。
- 合意で成立するため「契約内容は自由」
- 判断能力低下前から利用可能
- 死後事務も含めて委任できる
死後事務とは、死亡後の葬儀や死亡届、未払いの医療費の支払いなどの手配のことを言います。財産管理契約と同時に、死後事務委任契約を特約の形で締結することも可能です。
これに対して、財産管理委任契約のデメリットは次の通りです。
- 受任者を管理・監督する人がいない
- 受任者の権限が限られる
財産管理委任契約は当事者の合意により成立するため、任意後見制度や成年後見制度と異なり、事務内容を監督する人や機能がありません。
そのため、親族以外の第三者に委任する場合には、特に信用できる人に依頼する必要があります。
また、判断能力の衰えた委任者が誤った行為を行っても、財産管理委任契約の受任者には成年後見制度の後見人のように取消権がないため、委任者にとって損害となる行為を防ぐことができません。
なお、財産管理人の受任者は「医療行為(手術、延命治療等)の同意」もできません。
財産管理委任契約による受任者では、金融機関の窓口で預貯金の引出しや解約等の手続きを拒否される可能性もあります。
そのため、取引先の金融機関に財産管理契約の受任者による各種手続きが可能かを予め確認しておくと良いでしょう。
財産管理委任契約の活用方法
先ほど、老後の財産管理方法について、財産管理委任契約以外に、任意後見、成年後見、家族信託などの方法があると解説しました。
各制度を併用することでそれぞれのメリットを受けられ、デメリットを減らすこともできます。
任意後見契約・死後事務委任契約と併用
支援を受けることができない空白期間をなくすために、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を併用することが考えられます。
| ▽ 財産管理委任契約 | 判断能力がある段階 | 財産管理、療養看護 |
|---|---|---|
| ▽ 任意後見契約 | 判断能力が衰えた時点 | 財産管理、療養看護 |
| ▽ 死後事務委任契約 | 亡くなられた時点 | 死後の葬儀、医療機関・施設の 未払い費用の支払いなど |
任意後見契約は本人の生前にする財産管理や療養看護に対応するもので、本人が亡くなられた際に終了します。
そのため、財産管理委任契約の特約として死後事務についても依頼しておくことで、任意後見契約終了後の事務手続きまでカバーすることができ、まんべんなくあなたのご希望を叶えることが可能です。
なお、判断能力が衰える前は財産管理委任契約、判断能力の低下後は任意後見契約による財産管理へと移行する任意後見契約と組み合わせ方法を「移行型」と言うことがあります。
これに対して、将来の判断能力の低下にのみ備えて任意後見契約だけを締結しておくことを「将来型」、既に判断能力の低下がみられる場合に任意後見契約締結後すぐに家庭裁判所の任意後見監督人選任手続きをとり、すぐに任意後見事務を開始するケースを「即効型」と言うことがあります。
ただ、「即効型」については判断能力が衰えていることから、有効な法律行為をおこなえる状態にはないとして、公証人から任意後見契約公正証書の作成を断られる可能性があります。
公正証書で契約書作成
任意後見制度による支援を受けるための前提として、法律上公証役場で任意後見契約を公正証書で作成することが求められています。
そのため、財産管理委任契約と組み合わせる「移行型」を考えている場合には、財産管理委任契約書を公正証書と合わせて作成し書面にしておくと良いでしょう。
契約当事者間で契約締結後に「約束した」「約束していない」といったトラブルを避けることができるので安心です。
まとめ
老後の自分の財産管理や介護支援に不安がある場合、後見制度や家族信託、財産管理委任契約などがあります。
判断能力が十分あるうちに、ご自身の将来のことを考えて事前に備えておくことをおすすめします。
古山綜合法律事務所は、老後の財産管理から、ご家族のための遺言や生前贈与などの相続対策について実績があります。
また、既に判断能力を欠く常況にある方のためにする成年後見人選任の手続きも代行しております。
今まさに対応困難な問題を抱えておられるご家族様も、ぜひご相談ください。
遺産相続に関する初回相談は無料です。
弁護士が、ご希望を踏まえた最適な解決策の提案、解決までの流れや注意点について丁寧にアドバイスいたします。
お気軽に電話、WEBフォームなどからお問合せください。
- 老後の財産管理に不安なおひとりさま。
- 親族による財産の使い込みを防止したい。
- 判断能力があるうちに自分で後見人を選びたい。
- 生前から家族に財産管理・運用を任せたい。
老後の財産管理について、ご本人さまやご家族さまの不安や悩みをサポートするための法制度が用意されています。
財産管理に負担や不安を感じるとき、信頼できる第三者に財産管理を依頼する財産管理委任契約。
生前から財産の管理・運用を家族に任せるための家族信託。
親族による財産の使い込みが心配な場合は任意後見契約。
認知症でご本人さまの判断能力が既に衰えているケースでは成年後見制度の利用を検討するのが良いでしょう。
今、あなたが抱えている疑問や不安について、事情をお伺いしながら最適な解決策を無料でアドバイスしています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
老後の財産管理に関するサポート




相続に関する問題は、オーダーメイド性が高く、どのように契約や制度を利用すべきか、一般の方には悩ましい問題です。
古山綜合法律事務所では、初回無料相談で最適な問題解決のための選択肢をご提案しています。
ぜひお気軽に、お問い合わせください。
なお、相続財産の使いこみが発生している場合には、次のリンク先をご確認ください。
生前の財産の使い込み、死後の遺産の使込みのトラブルについて、使い込みを追及する側、使い込みを疑われ追及を受けている側のどちらの問題も対応可能です。あなたの主張をおこなうために必要な資料収集や交渉をおこないます。
必要書類の収集、書面の作成、裁判所や公証役場などに対する手続きの代行、関係者との窓口交渉などをおこないます。
手続き負担や、相手方となる親族などと直接話をする必要がなくなり、精神的な負担も大幅に軽減することができます。
弁護士費用
手続きや交渉を代行することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、適切な解決のためにサポートいたします。
老後の判断能力が衰えた際の財産管理、生前贈与や遺言書作成といった生前対策や相続税対策、相続全般に関する相談は初回無料で対応いたします ※。
少しでも不安や疑問が解消できるように、ご事情をしっかりお伺いし、具体的な対応策のご提案、個別のご質問にお答えいたします。
弁護士が財産管理委任契約書を作成します。
判断能力が低下した場合に備え、任意後見契約とセットでおこなうのが通常です。
弁護士が任意後見契約書の作成をサポートします。
任意後見契約は公正証書による必要があるため、公証役場との調整もおこないます。
家族がいない、または家族に負担をかけたくない場合に、葬儀や遺品整理、入通院・入所先の医療機関や施設への支払い、行政手続きなどおまかせいただけます。
弁護士が家族信託をフルサポートします。
具体的には、コンサルティング・信託契約書作成・公証役場や金融機関との連絡調整などをおこないます。
上記のほか信託契約書作成費用が別途発生します。
家庭裁判所への成年後見申立てのために必要となる、書類の収集や作成、申立書の作成や裁判所とのやりとりについて、すべてお任せ頂けます。
また、弁護士が家庭裁判所調査官との面接(受理面接)に同席することも可能です。

- 秘密厳守
- 一切無料※
“無料相談※” で具体的な解決
に向けスタートを。
に向けスタートを。
初回相談は無料ですが、解決に向けての道すじや解決方法を分かりやすくアドバイスさせていただきます。
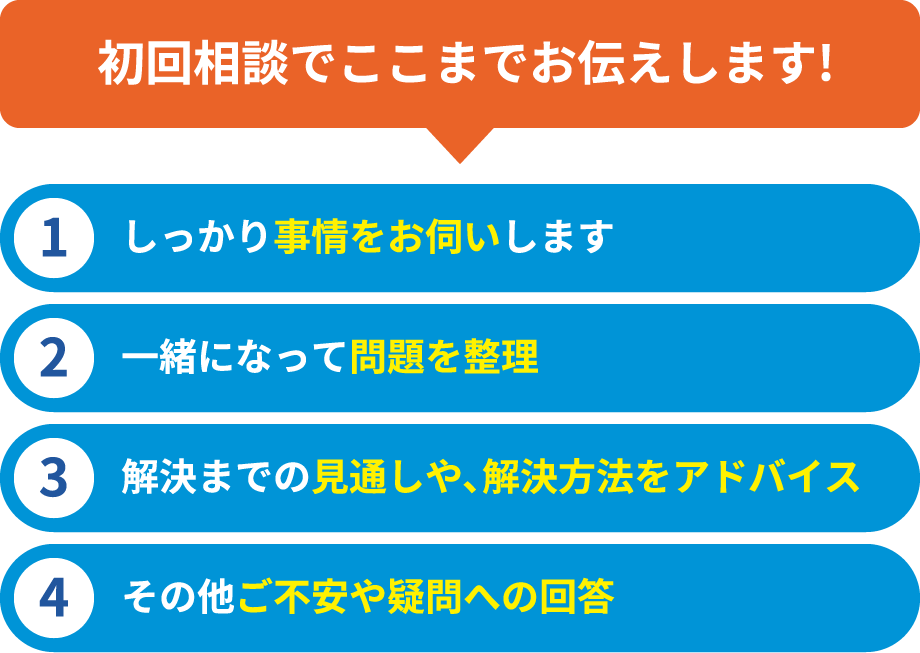

まずは事務局が受付対応
無料相談のご予約や、相談に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
- 無料相談の予約をしたい
- 相談前に問い合わせしたい
法律相談以外のお問い合わせ・相談予約をお伺いします。
お話ししながら、ご予約カンタン・安心です。
- はじめての弁護士相談で不安
- まず費用など問い合わせしたい
電話相談は行っていませんが、来所相談ではご持参いただいた資料やお話を伺いながら、
① 解決方法のアドバイス、②個別のご質問に弁護士がしっかりお答えします。
ぜひご来所の上ご相談ください。
都合の良い時間に問合せ
24時間受付中です。
- 忙しくて電話が難しい
- 自分のペースで問い合わせしたい