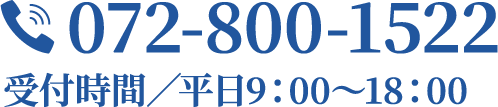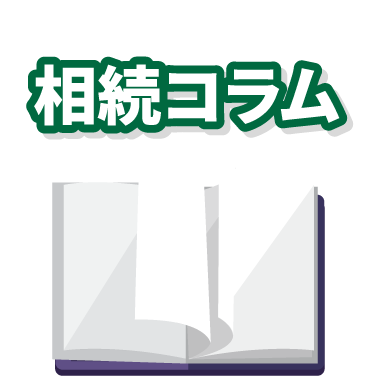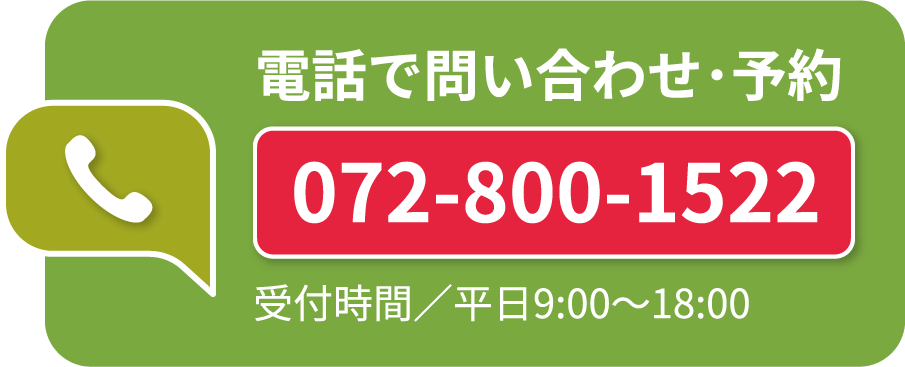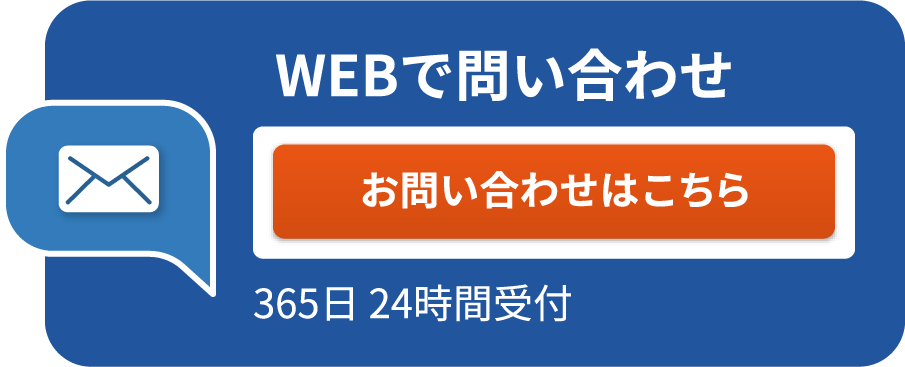使い込みの実体を把握するために金融機関の口座の取引履歴を調査します。
遺産の使い込み

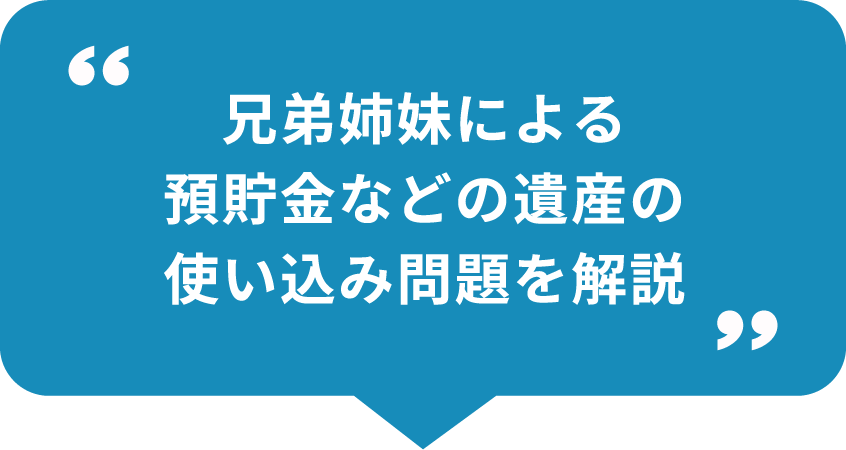
(生前)財産の使い込みの問題
相続トラブルで多い相談のひとつに、親族や兄弟姉妹による生前の財産使い込み、本人死亡後の遺産の使い込みがあります。
生前に財産の使い込みが発覚した場合、使い込まれた本人が交渉するか、裁判所を通して損害賠償請求や不当利得返還請求をおこないます。
ただ、本人において認知能力が落ちていて使い込みに気づけない、高齢で介護を受ける弱い立場にあり意見が言えないことがあります。
(生前)財産の使い込み事例
被相続人の財産の使い込みの発覚、使い込みへの不安を感じている方からの相談が当事務所では多くなっています。
- 浪費癖のある親族などに親の身柄を取られ、親に会わせてくれない
- 認知症など判断能力の低下した親の財産の使い込みが見られる
- ・キャッシュカードによるATMでの出金 ・預貯金口座の解約 ・不動産の売却や名義変更
- ・収益不動産の賃料収入の取込み ・証券口座の解約、株式の売却処分
上記のようなケースでは、相手方が親などの身柄を確保しており、近況・状況が分からないために使い込みの具体的な証拠がないことが多いです。
(生前)使い込みへの責任追及方法
生前に財産の使い込みがあった場合には、被害者である本人が損害賠償請求または不当利得返還請求をおこないます。
法律上の正当な理由なく、利益を得て他人に損失をあたえた人に対して、利益を返還するよう請求することです。
生前の財産使い込みにより、損失を与えられた本人が返還請求権を有することになります。
なお、本人が死亡した場合、相続人はこの返還請求権を承継することになり、生前の使い込みに対して権利を行使することになります。
本人に損失を与えることを認識しながらも不当に利益を得た人(受益者)に請求できるのは、「全額返還(受けた利益)」に、「利息+損害賠償金」を加えた金額を請求することができます。
不法行為とは故意(わざと)や過失により他人に損害を与えることです。
損害発生に対する賠償責任を追及するものです。
相続のタイミングで生前の使い込みが発覚した場合、相続人は本人(被相続人)の損害賠償請求権(または不当利得返還請求権)を相続します。
そのため、相続人が使い込みをおこなった人に対して請求します。
(生前)相手に使い込み事実の確認
本人が認知症や高齢による判断能力の低下をきっかけに、財産管理・療養看護や介護をおこなっていた親族が、自分たちの生活費などのために本人名義の預貯金口座からの勝手な引出しが増え、常態化してしまうことがあります。
しかし、本人の身柄や財産は相手親族に取り込まれていて、こうした生前の使い込みを事前に外部から確認することは難しいと言えます。
本人の死亡後、遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割の話し合いをおこないます。
遺産分割の対象となる相続財産を確定させるために財産調査をおこないます。
被相続人名義の預貯金口座、現金、証券、ゴルフ会員権、不動産、車両、宝飾品、絵画などの資産、借り入れといった負債を調査します。
例えば、相続時であれば相続人の立場で金融機関の預貯金口座を調べることができます。
使い込みの事実が疑われる場合には、残高証明書、10年間程度の取引履歴、解約済みの口座の有無などを照会します。
入手した取引履歴に、日常生活に必要のない不審なまとまった金額の出金がある場合、遺産分割協議にあたって、相手親族に引き出しの目的などを質問してみると良いでしょう。
生前に財産使い込みの事実は、本人の死亡時の財産調査の中で発覚することが多いです。
相続時の財産調査をしっかりおこなうことが、被害回復のための重要なポイントです。
なお、財産調査のための各種照会で、回答を拒否されることがあります。
こうした場合、裁判手続きの中で調査嘱託と呼ばれる裁判所を通して照会をかけることもできます。
(生前)被害の回復を求める方法
使い込みをした相手親族への責任追及、被害の回復方法は主に3つです。
- 任意で交渉する
- 弁護士を代理人に立てて交渉する
- 裁判所の訴訟手続き
使い込みの確たる証拠があるにも関わらず、相手がその事実を認めようとしない場合には、弁護士に依頼し交渉を継続するか、裁判所に「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」をおこなうことを検討します。
なお、弁護士に依頼することで使い込みの解明に本気であることや、裁判手続きも辞さないことが伝わる為、交渉が進む可能性があります。
また、弁護士には法律上の制度として「弁護士照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)」という手段により資料開示を受けられる可能性があり、財産調査代行のサポートを受けることもできます。
(生前)使い込みの指摘・責任追及への対抗策
もし、あなたが財産使い込みの疑いをかけられ、それが事実無根の場合には、可能な限り財産の使用に関する資料を準備し、疑念を払しょくできるように努めます。
あるいは、被相続人から遺産の前渡しである生前贈与(特別受益)として財産を受け取った場合には、その点を相手方に説明し反論する必要があります。
当事務所では、使い込みを追及されている側の方もサポートしています。 具体的な対処法などをアドバイスいたしますので、お気軽にお問合せください。
(生前)使い込みの刑事責任
通常、他人の金銭を盗み使い込むことは刑事罰(窃盗・横領)として罰せられます。
しかし、親族による財産の使い込みは犯罪として処罰されません(刑法244条)。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
※刑法235条は窃盗罪、同235条の2は不動産侵奪罪(奪うこと)です。
警察に相談しても対応して貰えないため、民事上の責任を話し合いや民事裁判で追及していくこととなります。
(生前)財産使い込みの予防策
多くの場合、相続に向けた前哨戦として本人の身柄を確保した親族は、他の親族に会わせようとしません。
そのため、親族間で疑いや不安が深まり相続前からトラブル発展することがあります。
同居する親族による使い込みを予防するための方法として次のものがあります。
- 任意後見制度の利用
- 成年後見制度の利用(判断能力が既に衰えている場合)
- 家族信託の利用
任意後見制度の利活用
任意後見制度は、本人が自身の判断能力が低下した際に、財産管理や療養看護をサポートする任意後見人を選んでおく制度です。
任意後見人には、家族以外に弁護士や司法書士といった法律のプロを選任することも可能です。
判断能力が低下した際に、任意後見人は家庭裁判所に手続きをおこない、サポートを開始します。
その際、任意後見人が今後の財産管理をおこなうため、使い込みのリスクを減らすことができます。
但し、既に身柄を相手親族に取られている場合、本人にコンタクトを取ることができず、当制度利用の前提である任意後見契約自体をおこなえないため、事実上利用が難しいと言えます。
成年後見制度の利活用
成年後見制度は、既に本人の判断能力が衰えている場合に、財産管理・療養看護の支援をおこなう成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
財産管理権が成年後見人に移り、ケースによっては後見事務を監督する成年後見監督人も選ばれることから適切な管理がおこなわれることが期待できます。
成年後見人の候補者として親族を推薦することも可能ですが、最終的には家庭裁判所が適任者を選任するため、第三者である弁護士や司法書士が選ばれることもあります。
家族信託制度の利活用
家族信託は、本人の財産の信託を受けた人(受託者)が運用管理をおこないます。
判断能力の低下前から、積極的な財産の運用が可能で、相続発生時にもスムーズな財産の承継ができるといったメリットがあります。
信託契約に従って財産が運用管理されるため、使い込みを予防することが期待できます。
生前の財産使い込みの注意点
裁判手続きで生前の財産の使い込みを争いたい場合、消滅時効に注意が必要です。
時効にかかると債権が消滅し、不当利得の返還や損害賠償の請求ができなくなります。
反対に、財産の使い込みを指摘された方は、時効により請求権が消滅していることを主張し反論することができます。
なお、消滅時効にかかっていることを知らずに返済義務を認めた場合、その債務の承認は有効です。消滅時効を主張できるかどうか確認することが大切です。
- 権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
- 損害および加害者を知ってから3年
- 不法行為の時から20年
(死後)親の遺産・相続財産の使い込み
本人が亡くなった際に、生前の財産、相続後に遺産の使い込みが発覚することがあります。
(死後)相続財産・遺産の使い込み事例
相手方が被相続人の身柄を取っていた場合、キャッシュカードや印鑑、不動産の権利証などが手元にあることが多く、それらを使って死亡後に遺産の使い込み、名義変更など勝手な処分が行われているケースがあります。
- 死亡直後に銀行口座から無断引出し
- 知らぬ間に遺言書が作成されていた
- 被相続人に認知症が疑われる時期に遺言書作成
また直接的な遺産の使い込みではありませんが、知らぬ間に相手に有利な内容の遺言書が作成されていることがあります。
遺言書をもとに遺産を処分され、法律上最低限保障されている相続分さえない、というトラブルも見られます。
相手に有利な遺言書が残されていたり、認知症などが疑われる時期に遺言書が作成されていたりする場合の相続トラブルについて解説しています。
(死後)使い込みへの責任追及

本人の死後の遺産の使い込みに対する被害回復の方法は、① 当事者で話合い(弁護士を代理人に立てて交渉する)、② 遺産分割調停、③ 訴訟があります。
遺産相続の使い込みがあった場合の、解決までの流れについて解説します。
相続財産調査
遺言書が残されている場合、その内容が優先されます。
なお、遺言書作成の過程で、偽造・変造などの不正、無理やり作成させた疑いがある場合には遺言書の有効無効を争うことになります。
医療機関、介護事業者(デイサービスや介護施設など)、市区町村にそれぞれ医療記録、介護記録、介護保険認定資料などを取り寄せたうえで認知能力の低下(認知症など)の記載がないか、いつからその症状が見られるのかなど遺言能力があったかを確認することがあります。
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割の話し合いをおこないます。
分割対象となる遺産を確定する必要がある為、まずは相続財産調査をおこないます。
- 預金・借入金(銀行、信用金庫、信用組合、JA等への開示請求)
- 出資金(信用組合など)
- 株式・投資信託(証券保管振替機構、証券会社等への照会)
- 不動産(市区町村役所で名寄帳等、法務局で登記事項証明書)
- 車両(自動車車検証で所有名義確認)
銀行等で口座の有無、残高証明、取引明細などを取寄せます。
出金、振込で不審な出金がないかを確認します。
また、一般的に金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で口座は凍結されます。
相手に預貯金通帳、印鑑、キャッシュカードがある場合、速やかに被相続人の死亡の事実を金融機関に伝えて口座を凍結することで勝手な出金や振込を防ぐことができるため安心です。
不動産については、被相続人名義であった土地・建物について全部事項証明書を取り寄せ、処分による所有名義人の変更がないか、借り入れの担保として抵当権の設定がなされていないかなどを確認すると良いでしょう。
なお、相続財産調査は、弁護士に依頼し弁護士会を通して照会する方法と、訴訟手続きの中で裁判所を通して照会することもできます。
交渉による解決
相手が使い込みを認めた場合、遺産分割の中で使い込みの内容を踏まえて、取り分を調整するなどして遺産分割協議による解決を目指すのも解決のひとつです。
裁判所手続きによる解決
相手との話し合いで解決できない場合、遺産分割調停による解決を検討します。
2018年の民法改正により、使い込みをした相続人以外の相続人全員の同意があれば、使い込まれた遺産を調停の対象にすることができるようになりました。
調停手続きは、裁判官(家事審判官)と調停委員を交えた話し合いによる円満な解決を目的にした手続きです。
調停による解決が難しい場合、調停は審判手続きに移行します。
審判は、裁判所としての判断をおこなうものです。
審判に不服がある場合には、即時抗告の手続きをおこないます。
調停ではなく、① 「不当利得返還請求」、または② 「不法行為に基づく損害賠償請求」をもとめる裁判を提起することも可能です。
なお、相手から「生前贈与として受け取った」との反論を受け、使い込みの追及が難しい場合には、生前贈与とされる財産の価格を相続財産に加算して相続分を計算しなおすことを求めます(相続分の持戻し)。
特別受益の持戻しも難しく、あなたの法律上保障された相続分(遺留分)を侵害されているときは遺留分侵害額請求をおこなうことになります。
遺留分侵害額請求により、遺留分の支払いを受けた場合、その取得内容に応じて相続税申告(または修正申告)の必要性が生じる事があります。
訴訟による解決も複数の手段があり、内容に違いがあります。
そのため、どの手段をとるのが良いかは個別の状況により異なりますので、弁護士に相談されると良いでしょう。
(死後)使い込みを疑われている方
もし使い込みを疑われている場合、それが事実無根の時には、可能な限り財産の使用に関する資料を準備し、疑念を払しょくできるように努めます。
あるいは、被相続人から遺産の前渡しである生前贈与(特別受益)として財産を受け取った場合には、その点を相手方に説明し反論する必要があります。
(死後)使い込みをしていた方
実際に使い込みをしていた場合、使途不明金に関する損害賠償請求や不当利得に対する返還請求を拒むことは難しいでしょう。
ただ、あなたが相続人で被相続人の療養看護の負担をしていた場合には、遺産分割協議のなかで寄与分を主張して、実質的に使途不明金の返還額を減らすよう交渉することができるかもしれません。
財産・遺産使い込みの請求にあたっての注意点
財産・遺産の使い込みの返還を主張するにあたり、問題になりやすい点について解説します。
証拠の収集
使い込みを指摘するにあたり、確かな証拠が必要です。
訴訟では権利を主張する側に立証責任があります。
つまり、使い込みを指摘する側は主張を裏付ける証拠の提出がなければ、裁判官に不当利得の返還や、損害賠償を認めてもらうことは難しいでしょう。
証拠集めの範囲や訴訟による解決の見込みなど、一度弁護士に法律相談を受けておくことをおすすめします。
時効
不当利得、不法行為に基づく損害賠償請求、遺留分侵害と消滅時効があり、請求には期限があります。時効を迎える前に、請求をおこなうようにしましょう。
使い込みを疑われ請求を受けた側にとっても、時効を確認することは大切です。
時効が成立しているにも関わらず、相手の主張を認めると消滅時効の完成を主張できなくなります。
そのため、使い込みの疑いをかけられた際には、消滅時効の主張は可能か、どのような反論が出来るのかを含めて弁護士に相談しておくと良いでしょう。
相手方に資産がない
話し合いが決裂し訴訟で解決しようとする場合、相手に資力(資産)があるか確認しておく必要があります。
相手に資力がなければ、例え裁判で損害賠償などを認める勝訴判決をとったとしても、実際には被害を回復することは困難です。
また、相手の財産が訴訟をしている間に散逸してしまう可能性がある場合には、裁判の前に財産の処分を禁止する保全手続をとる必要があります。
財産を処分されるリスクが考えられる場合には、弁護士に相談し早めに対応をすることが大切です。
まとめ
生前の財産の使い込み、死後の遺産の使い込みは、証拠収集や交渉といった負担が大きいトラブルの一つです。
古山綜合法律事務所では、相続財産の使い込みに関する問題の解決実績があります。 交渉から訴訟までをトータルサポートいたします。
まずは初回無料相談(60分)にて、具体的解決に向けて法的な対処方法、進め方をアドバイスいたします。
泣き寝入りや、後悔をしたくない方は、事前にご予約の上、当事務所までぜひお気軽にご相談ください。
なお、弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、弁護士にご依頼頂くことで、解決に向けた証拠や申立必要書類の収集、交渉・裁判手続きの代理、書類の作成といった手間・事務処理の負担を大幅に減らすことができます。
弁護士が代理交渉をおこないますので、直接相手と話をしなくてもよくなるため、精神的なご負担も軽くできるメリットも大きいと思います。
遺産相続問題のサポートについても気なる方も、ぜひお気軽にお問い合せください。
- 親族・きょうだいが、親の財産を使い込んでいる。
- 相続財産の内容を開示しない。
- 相続財産の使い込みを疑われ、裁判を起こされた。
- 相続財産を取り戻したい。
高齢や認知症になっている親の預貯金が、生前や死後、親族や第三者によって使い込まれた・取り込まれたと疑われることで、トラブルになる場合があります。
トラブルとしては、預貯金の勝手な使い込みがほとんどですが、まれに株式・投資信託の売却、所有不動産の売却・名義変更、保険の解約返戻金の取り込みなどが挙げられます。
使い込みを追求したい側としては、相手に親の身柄を取られているために親の状況や財産の内容が分からないなどによって、疑い深くなっていることがあります。
また、使い込みを追及された側からすれば、親の介護などのために適切に財産を管理・使用したにも関わらず、相手から疑いを持たれることに、不満や怒りの感情が生じる場合があります。
財産・遺産の使い込みについての問題は、お互いの立場に立って、トラブルを具体的に解決していくための対応が必要となります。
遺産使い込みへのサポート




使い込みには2パターンあります。
① 生前の財産使い込み、② 死後の遺産の使込みです。
相続人が被相続人の生前に財産を使い込んでいたことが発覚したにもかかわらず相手が使い込みを否定している場合や、財産を使いこんだのが第三者の場合は、訴訟を提起します。反対に、相続人が使い込みを認めた場合、使途不明金を遺産の総額に含めて計算したうえで、遺産分割をおこないます。
相続人が被相続人の死後に遺産を使い込んでいたことが発覚したにもかかわらず相手が使い込みを否定している場合や、遺産を使いこんだのが第三者の場合に、訴訟を提起するのは、使い込みが生前だった場合と同じです。 反対に、相続人が使い込みを認めた場合、使途不明金を遺産の総額に含めて計算したうえで、遺産分割をおこなうのも、使い込みが生前だった場合と同様です。
話し合い、裁判手続によって解決するためには、「財産・遺産の使込み」の事実を立証できる「証拠」を確保することが重要なポイントです。
古山綜合法律事務所では、資料収集から収集後の分析、遺産分割の交渉代行や訴訟代理までをトータル・フルサポートいたします。
初回無料相談では、今後の対応について具体的なアドバイスをさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
まずは話し合いによる解決ができないかを模索します。
話し合いによる解決が難しい場合、裁判を起こします。
裁判では、基本的に権利を主張する側に立証責任があります。
そのため、訴訟に進む場合には、証拠を確保していることが大切です。
訴訟では、最終的に裁判官の判断を求めることになります。
ただ、裁判手続きの中で裁判官から和解を勧められることもあり、和解で終了することも多いです。
なお、遺産分轄調停や審判が進んでおり、あとから預貯金の返還請求訴訟を起こした場合でも、その後の進展によっては、遺産分割手続での解決が可能か、改めて検討することも可能です。
生前の財産の使い込み、死後の遺産の使込みのトラブルについて、使い込みを追及する側、使い込みを疑われ追及を受けている側のどちらの問題も対応可能です。あなたの主張をおこなうために必要な資料収集や交渉をおこないます。
弁護士費用
手続きや交渉を代行することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、適切な解決のためにサポートいたします。
遺産の使い込み、相手方が財産を開示しないことについての争いだけでなく、相続全般に関する「来所相談(平日・60分)」は初回無料で対応いたします ※。
少しでも不安や疑問が解消できるように、ご事情をしっかりお伺いし、具体的な対応策のご提案、個別のご質問にお答えいたします。
相続財産の使途不明金を調査し分析をすることで、具体的な請求へとつなぎます。
①簡易な調査の場合、金融機関の口座を対象に取引履歴の取得・確認、②詳細な調査の場合、①に加えて入出金一覧表の作成、医療記録・介護記録の精査などをおこないます。
預貯金や医療記録・介護記録などを弁護士が調査いたします。
具体的には、②の「詳細な調査プラン」では、弁護士が、金融機関や医療機関、自治体などに対して取引履歴やカルテなどを請求し、不審な出金などがないか調査します。
裁判所外での財産・遺産の使込みへの対応をおこないます。
具体的には、内容証明郵便による書面の送付や、相手方との交渉代理をおこないます。
なお、遺産分割をご依頼頂いている場合には、使途不明金についての問題も合わせて対応するため、上記費用はかかりません(0円)。
任意交渉による解決が難しい場合、裁判所での解決を求めます。
裁判書類の作成、資料の収集、期日の裁判所出廷などにより、あなたに代わって主張をおこない適切な解決のための弁護士活動をおこないます。
交渉対応から依頼頂いている場合は22万円、裁判対応からのご依頼の場合は44万円となります。

- 秘密厳守
- 一切無料※
“無料相談※” で具体的な解決
に向けスタートを。
に向けスタートを。
初回相談は無料ですが、解決に向けての道すじや解決方法を分かりやすくアドバイスさせていただきます。
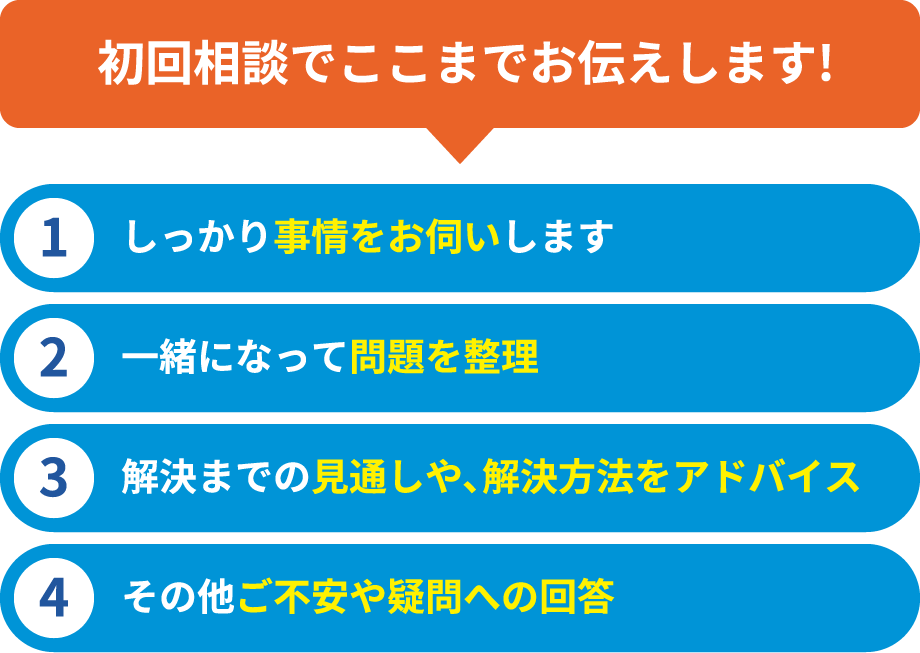

まずは事務局が受付対応
無料相談のご予約や、相談に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
- 無料相談の予約をしたい
- 相談前に問い合わせしたい
法律相談以外のお問い合わせ・相談予約をお伺いします。
お話ししながら、ご予約カンタン・安心です。
- はじめての弁護士相談で不安
- まず費用など問い合わせしたい
電話相談は行っていませんが、来所相談ではご持参いただいた資料やお話を伺いながら、
① 解決方法のアドバイス、②個別のご質問に弁護士がしっかりお答えします。
ぜひご来所の上ご相談ください。
都合の良い時間に問合せ
24時間受付中です。
- 忙しくて電話が難しい
- 自分のペースで問い合わせしたい