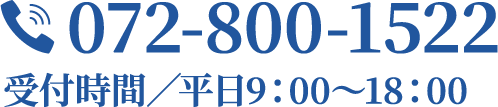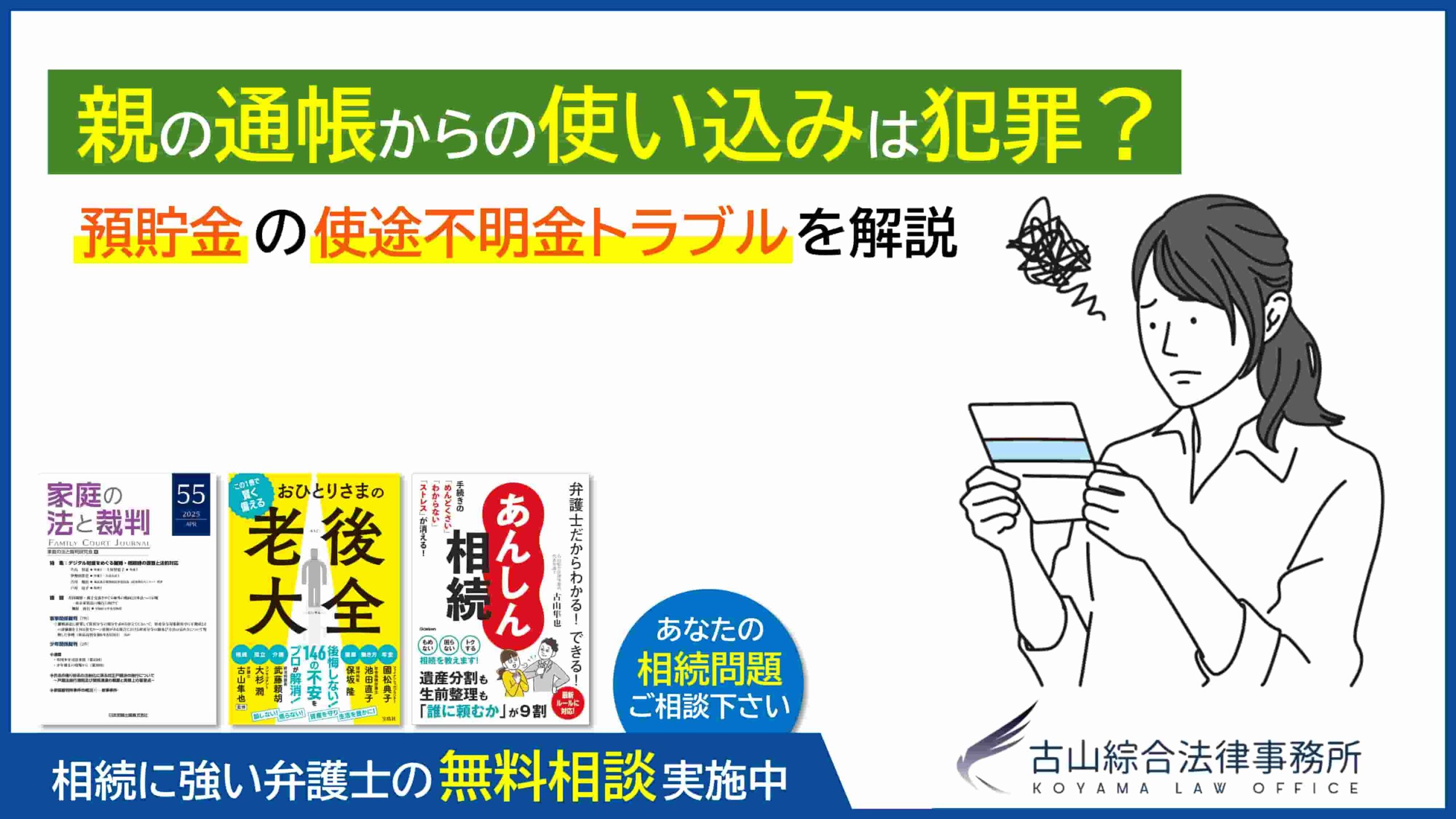1.親の預貯金の使い込みのトラブル
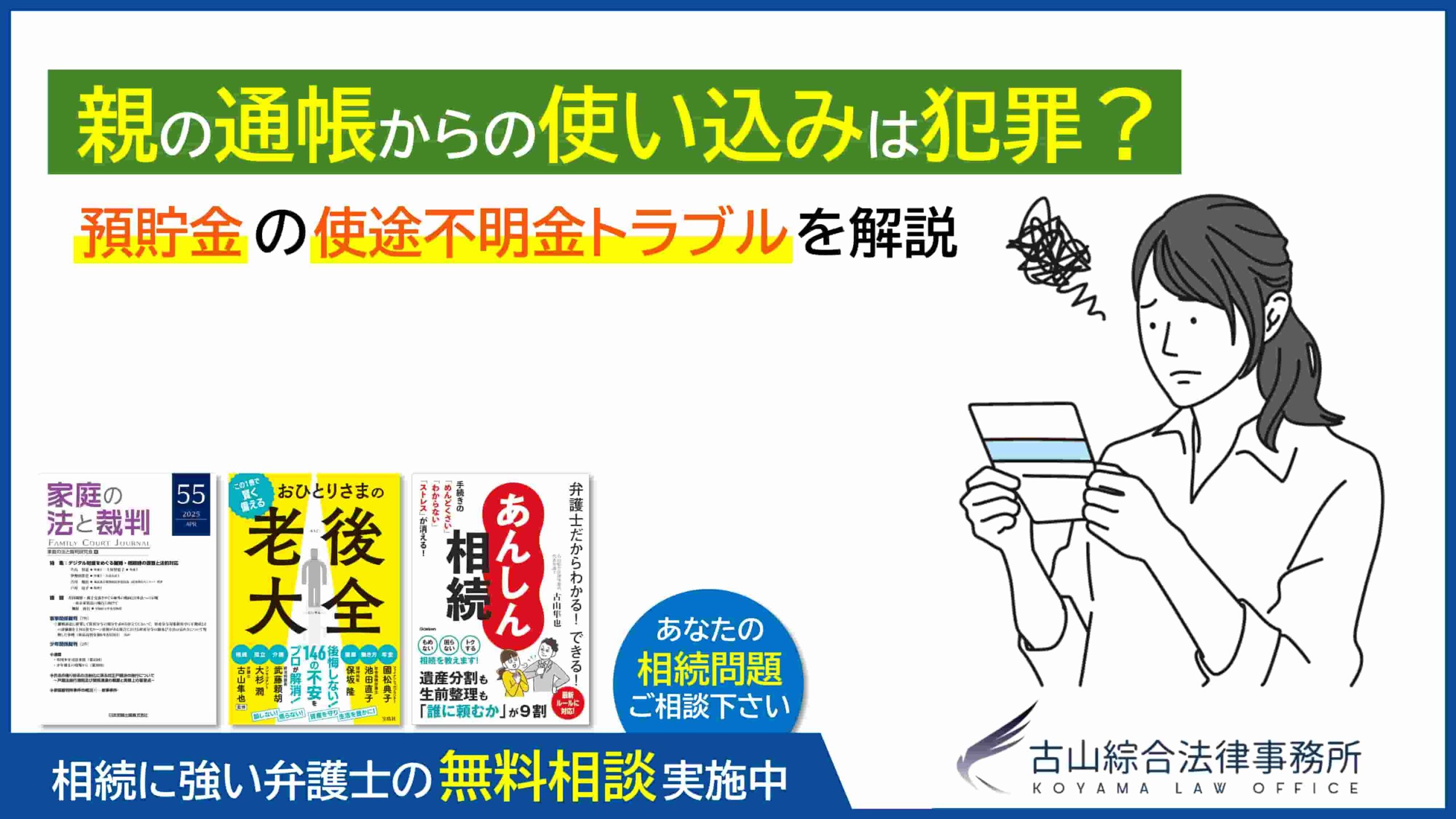
親と同居していたり、介護や看護をしている家族が親のキャッシュカードや通帳から勝手に預金を引き出し、使い込んでしまうトラブルのご相談はよくあります。
また、親が亡くなってから銀行口座が凍結するまでの間に、預金通帳やキャッシュカード、印鑑などを持っている家族が親の銀行口座から預貯金を出金してしまうのもよく聞く話です。
他の相続人による親の預貯金の使い込みが疑われる場合において、どうすれば使い込まれた分の財産を取り戻すことができるのか、また使い込みを疑われた場合にはどのように反論すべきかについて解説します。
(1)家族による預貯金の使い込みは犯罪にはならない
一般的に他人のキャッシュカードや通帳を使用し、無断でATM機から現金を引き下ろすと窃盗罪に該当し、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。
また、他人から預かったキャッシュカードや通帳を無断で使用すると横領罪に該当します。
しかし、それが被相続人の配偶者や子ども、同居の親族など、家族内で起きたことであれば刑法第244条に規定された「親族相盗例」によって刑が免除されます。
参照│刑法第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
家庭内の問題について法律は関与せず、自治的解決に委ねるべきという考え方が古くからあり、親族相盗例は一定の親族間で特定の罪を犯した際に、その人の刑を免除したり、被害者などからの告訴がなければ起訴できないこととする特例です。
そのため、「親族が親のお金を勝手に取った!」と警察に相談しても、刑が免除されてしまうので相手にしてもらえないでしょう。
とはいえ、たとえ親であろうと自分のものではない預貯金を勝手に引き出す行為は、他の相続人からすれば許されざる行為です。
ましてや、使い込みによって財産が減り、自分の相続分が減ってしまうため見過ごすことはできない問題です。
(2)民事上の責任追及
親の預貯金を使い込んでも刑事罰には問えませんが、民事上で責任を追及することは可能です。
具体的には「不法行為に基づく損害賠償請求」または「不当利得返還請求」という方法を使って使い込まれた金額を取り戻していくことになります。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民事上での責任は、追及する側が調査をして使い込みをした事実、金額などを明らかにする必要があります。
話し合いや調停手続きで解決することもありますが、裁判になった場合には、裁判官に「親に無断で」「預金を引き出し」「使い込んだ」事実を認めてもらえるように立証しなければなりません。
そのため、使い込みがあったことを証明するための調査や裁判所手続きについては、経験が豊富な弁護士に依頼して進めていくことが大切です。
2. 預貯金の使い込みを取り戻す方法
相手が使い込みを認めてくれるようならば当事者同士で話し合って解決を試みるのが一番です。
しかし、引き出した事実は認めても「親から頼まれた」「親の介護をしているお礼としてもらった」などと主張されたり、話し合いに応じてくれないケースも少なくありません。
使い込みが多額に及ぶ場合は他の相続人の相続額にも大きく影響します。
その場合は、裁判所手続きなどを利用して解決を進めていくことになります。
(1)親(被相続人)の生前に使い込まれた場合
親が存命の場合に使い込みがわかった場合は、使い込みがあった銀行口座の名義人である親本人が子に対して「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」をおこないます。
既に親は他界しているものの、使い込まれたのが生前である場合は、親に代わって他の相続人が「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」をおこないます。
これは本来、親が持っていた損害賠償請求権または不当利得返還請求権を、相続したことにより行えるものです。
(2)親(被相続人)の死後、使い込まれた場合
通常、銀行や郵便局などの金融機関は口座名義人の死亡が確認できると、その預貯金口座は凍結されます。
しかし、死亡後に口座が凍結する間には時間差があり、その間にキャッシュカードや通帳、暗証番号を管理していた相続人であれば、簡単に預金を引き出すことができます。
被相続人の預貯金は、名義自体は被相続人のものですが、亡くなった時点から遺産分割が終了するまでの期間は相続人全員の共有財産となります。
したがって、共有財産である預貯金を相続人の1人が無断で引き出すことは、他の相続人の権利を侵害していることになります。
そのため、他の相続人は不正出金した相続人に対して、権利が侵害された限度で「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」をおこなうことができます。
(ア)遺産分割協議で解決を図る
使い込んだ相続人がその事実を認め、引き出した金額分の返還の意思があるようなら、当事者間で話し合って解決することができます。
遺産分割前であれば、使い込まれた金額を戻してもらい、相続人全員で遺産分割協議をおこない、全員が合意のもと遺産分割をおこないます。
(イ)遺産分割調停(家庭裁判所)を利用する
相続開始後の親の通帳からの預貯金の使い込みが発覚したような場合において、使い込んだ相続人以外全員の同意があれば、遺産分割調停などの対象にできるようになりました(法改正前までは、相続人全員の同意がなければ遺産分割の対象とならず、裁判をおこす必要がありました。)。
当事者同士の話し合いによる解決が難しい場合、使い込みを含めて遺産分割調停のなかで解決を図ることができます。
調停では調停委員が中立的な立場でそれぞれの主張を聞き、遺産分割の合意成立のために仲介してくれるため、当事者同士で直接対峙するよりも冷静に話し合うことができるのがメリットです。
ただし、遺産分割調停を申し立てるにあたって、遺産分割をおこなうにはまずは相続財産がどれだけあるのか、範囲を確定させる必要があります。
また、使い込まれた金額がいくらかが判明していないと交渉を進めるのはむずかしいといえます。
(ウ)訴訟手続き(地方裁判所)をおこなう
当事者同士での話し合い、調停での解決がむずかしい場合は、裁判所に「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」の申し立てをおこない、使い込んだ相続人の責任を追及していくことになります。
訴訟手続きでは、権利を主張する側が使い込みの事実を立証しなければなりません。
何をどう調べればいいのか調査の仕方と地道な作業が求められるため、相続問題に詳しい弁護士のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
3.通帳・預貯金の使い込みの調査方法
預貯金の使い込みについて調べるには、まずは金融機関の取引履歴を調べます。
金融機関から取引履歴の開示を受け、生活費などの支出以外に、まとまった金額の出金など不審な取引がないかなどを確認します。
また、親の存命中に預貯金が引き出されていた場合には、親の意識レベルを調べることで同意があったか、無断で行われたかを判明することもあります。
親が寝たきりであったり、認知症を患い意思能力がなかった場合には、無断で引き出された可能性が高いです。
これらの資料をもとに、親の通帳からの使い込みが疑われる相手方に対して、親のために使われたかどうかなどの説明を求めることで、引き出された金銭を使い込んだかどうかを明らかにしていきます。
例えば、本人の生活費や事業運営費用、入院費、介護費用、葬儀費用などに使用したと説明を受けた際に、明細や領収書の提出を求めるようにします。
このような証拠書類を集めるには、金融機関や医療機関、介護施設などの記録の取り寄せが必要です。
また、取寄せた取引履歴やカルテ、診断書、介護記録、各種支払い履歴などの確認、分析や検討には時間や知識が必要になることがあります。
例えば、医療記録から意識レベルがどの程度であったかなどを読み解くだけでなく、使い込みの相手方との交渉の中で、どのように活かすのかは一般の方にとって難しいものです。
どのような資料が必要かの検討や、取り寄せた書類を分析し証拠化すること、相手との交渉までを任せられるのは弁護士だけです。
使い込みの問題は、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。
(1)預貯金の取引履歴を調べる
被相続人が取引していた金融機関を把握している場合は、その銀行や郵便局などに対して取引履歴を照会します。
ただし、使い込みが疑われる相続人が親と同居、あるいは親と近しい関係性で財産管理をしている場合には、被相続人がどこの銀行を利用していたかさえわからないこともあります。
その場合には、過去に住んでいた地域を含め、親の自宅周辺にある金融機関をすべて調べる必要があります。
仕事関連で会社指定の銀行があったり、最近ではネットバンクを利用している可能性もあるので、可能な限りすべての金融機関を調べてみましょう。
また、公証役場、法務局で遺言書が保管されていないか照会をかけておきましょう。
遺言書の財産目録の記載から預貯金の存在が発覚することがあります。
被相続人名義の口座が見つかれば解約から数年分の取引履歴を取り寄せ、不審な引き出しや移動がなかったかを調べます。
引き出された支店名やATMなのか窓口なのかなどの情報は、誰が引き出したのかの特定にもつながります。
(2)親の認知能力を調べる
使い込みがあったと疑われる時期に親の健康状態がどうだったかを調べることで、預貯金の引き出しが親の同意のもとおこなわれたか、無断でおこなわれたものかがわかる可能性があります。
入院していたり要介護認定を受けて介護施設に入居している場合は、自身で預金を引き出すことができなかったと判断できます。
また、親が病気などで意識不明や混濁している場合や認知症などで意思能力が低下しているような場合は、無断で引き出された可能性が高くなります。
本人の状況を確認するために、各医療機関や介護施設にカルテや診断書、看護記録、介護記録などを取り寄せます。
医療機関の記録は医師法により保管期間は5年間と決まっているため、古すぎる記録は取得できないこともあるので注意が必要です。(医療機関によっては、診療が完結した日から5年を超えてカルテが保管されていることもあります。)
・弁護士ならスムーズに各種調査がおこなえる
金融機関や医療機関などの各機関への問い合わせには地道な作業と時間が求められます。
弁護士であっても地道な作業であることは変わりありませんが、弁護士には弁護士法第23条の2により、弁護士会を通して各機関に調査をおこなうことができる場合があります。
弁護士法第23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
また、これまで多くの相続問題を解決した経験と実績のある弁護士なら、培ってきた財産調査のノウハウにより効率的かつ正確に調査をおこなうことができます。
銀行や医療機関は受付時間が平日の日中であることが多く、直接足を運ばなければならないこともあり、件数が多い場合には非常に煩雑です。
弁護士費用はかかりますが、弁護士に依頼することで時間的負担や労力を大幅に軽減することができます。
4.使い込みに対する請求手続きの注意点
預貯金の使い込みに対しての請求手続きには期限・時効があります。
不当利得返還請求は、使い込みの事実を知ってから5年、使い込みが発生してから10年が経つと請求権がなくなり、訴訟手続きなどができなくなります。
不法行為に基づく損害賠償請求もまた、使い込みの事実が知ってから3年、使い込みが発生してから20年が経つと請求権がなくなるので注意が必要です。
また、使い込みの根拠となる書類の取り寄せについても、各機関での保管期間を過ぎてしまうと破棄されてしまいます。
会計帳簿の保存義務の期間が10年となっているので、金融機関の取引履歴は原則的に請求した時点から10年前までしか遡ることができません。
また、医療機関でのカルテの記録も保存期間は治療が終わった日から5年間とされています。
以上のことから、使い込みが発覚したらすぐに行動に移すことが大切です。
特に被相続人の生前の使い込みに関しては、証拠となる記録が失われてしまう可能性があるため、急いだ方がいいでしょう。
5.家族による預貯金使い込みを防ぐ方法
親の預貯金を無断で使い込んだことを他の相続人が個人で証明していくには非常に労力がかかります。
また、相続人間で使い込みのトラブルが起きてしまうと、互いに不信感や不満が募り、修復不可能なところまで関係性が壊れてしまうこともあります。
そこで、親が元気なうちから後のことを考えて認知症対策をしておくことが大切です。
(1)家族信託の活用
家族信託とは、本人の生前から信頼する家族に自分の財産の運用や管理、処分などを任せられる財産管理のための制度です。
認知症など本人の判断能力が衰える前から、家族が代わりに積極的な資産運用や管理ができたり、自由度と柔軟性の高い内容で財産管理ができるため、最近注目を集めています。
遺言書では本人の死後、財産を誰に渡すかということまでしか決められませんが、家族信託なら財産の承継順位まで決めておくことができます。
他の制度ではむずかしい財産管理も家族信託なら実現可能なケースも多い反面、比較的新しい制度のため、安易に契約を結んでしまうと思わぬトラブルが起きる可能性もあります。
家族信託により財産の管理をおこなう受託者に権限が集中することで他の相続人が不満を抱いたり、相続時の遺留分侵害の可能性なども考えられるため、財産状況や家族の関係性、希望する相続内容などを踏まえて、家族信託の活用が妥当かどうか検討する必要があります。
(2)任意後見制度の活用
任意後見制度とは、将来的に認知症などによって判断能力が低下するおそれがある人が、健康なうちにあらかじめ財産管理などを任せる後見人を指名して契約を結んでおく制度です。
判断能力が不十分になったときに備えて、日常生活の支援方法や財産管理・処分方法などについてあらかじめ決めておくことができます。
いざそのときがきた際には後見人が本人に代わり決めた内容に沿って支援をおこなってくれます。
任意後見人には、本人が希望する人物を任意に選ぶことができます。
家族や親族、信頼のおける他人でも可能で、弁護士や司法書士などの専門家を指名することもできます。
任意後見人制度は重要な契約であるため、契約には公証役場で書類を作成することが義務付けられています。
また、本人が元気なうちは効力を発揮せず、判断能力が低下し、後見人が必要となった際に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されます。
(3)成年後見制度の活用
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な人が生活のなかで不利益を被らないように、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任し、財産管理や契約行為の支援する制度です。
任意後見人制度では任意の人を後見人に指名することができますが、成年後見制度では家庭裁判所が適している人を選任するため、後見人を自分で選ぶことができません(但し、申立ての際に、親族や弁護士などの専門家を推薦することはできます。)
ただ、本人に成年後見人が選任されると、財産に関してその管理下におかれるため、親の通帳からの使い込みの心配はなくなります。
6.預貯金の使い込みを疑われた場合の対応
親と同居していたり近くに住んでいたため老後の介護をしてあげていただけなのに、想定よりも預貯金が少ないと他の相続人から使い込みを疑われるケースもあります。
老後の親の面倒をみていない親族から、相続時に「遺産をよこせ」と権利だけはしっかりと主張されるケースは少なくありません。
「他の相続人は生前、親の世話など一切しなかったくせに、あまつさえ使い込みまで疑ってくるなんて…」と憤りを感じるのもしかたのないことです。
しかし、感情にまかせて反論してしまうと、後の主張に矛盾点が生じ、相手方や裁判所からの信頼が失われ不利な結果につながることもあります。
また、身に覚えがないからと放置していると訴訟に発展するなどの大きなトラブルになる可能性もあります。
まずは落ち着いて慎重に対応方針を検討し、適切に反論するようにしましょう。
相手が喧嘩腰で話し合いに応じるようでなければ、早めに弁護士に相談するのもおすすめです。
(1)預貯金の使途を証明する証拠を集める
話し合いの段階ならば、まずは「何故使い込んだと思ったのか」その根拠について、相手に説明を求めましょう。
反論としては、預貯金を自分が引き出したものなのか、違うのか、自分が引き出した場合は親の意思によるものなのか、違うのか、引き出したお金は何に使ったのか、などを明確にする必要があります。
親の生活費や治療費、介護費用など、親のために使ったのであれば、それらを証明できるようなレシートや領収書などがあれば、より反論に説得力が増します。
これに対して、実際に自分や自分の家族のために使い込みをしてしまった場合、どうせバレないだろうと思って相手に嘘をつかないことです。
後から引き出した証拠として銀行口座の取引履歴などが出てきた場合に矛盾点が生まれ、相手の信用を失ってしまうおそれがあります。
また、訴訟を提起された場合は無視せず、必ず対応するようにしましょう。
裁判の期日に無断欠席した場合、訴訟を提起した側の主張が一方的に認められてしまいます(民事訴訟法第159条第1項)。
訴訟になった場合は相手方が弁護士に依頼しているケースが多く、法律のプロを相手に反論しなければなりません。
対等に渡り合い、しっかりと反論するためには、自身も弁護士に依頼することをおすすめします。
(2)生前贈与を主張する
引き出された預金のうち、親から認められて自分の生活費などに充てた場合は生前贈与を主張することになります。
贈与契約書などがあれば大きな根拠となりますが、親子間では書類がない場合がほとんどです。
日記やメールなど、贈与した事実が確認できる場合は生前贈与と認められることもあります。
ただし、親が亡くなる10年前までの生前贈与は、「特別受益」に当たる可能性があります。
特別受益に当たる場合は、生前贈与として貰った金額を財産に戻して遺産分割を考えることになります。
他方、10年を超えてされた生前贈与は、特別受益の対象外となります。
7.まとめ
預貯金の使い込みは、引き出した事実までは簡単に確認できますが、引き出した人物の特定や使い込んだ事実を証明するのはむずかしく、解決には地道な証拠収集や交渉が求められます。
また、事実はどうあれ、使い込みを疑った時点で相続人同士の信頼関係を損ない、相手に対しての不信感や憤りがつのり、当事者同士の話し合いで解決するのは困難になりがちです。
しかし、だからといってあきらめてしまうのではなく、使い込まれたのが事実であれば、当時の情報を丹念に集めて照合し、分析することで証明することは不可能ではありません。
これまで多くの相続問題を解決した経験と実績のある弁護士なら、培ってきた財産調査のノウハウにより効率的かつ正確に調査をおこなうことができます。
また、弁護士が代理人となって交渉することで、感情的な対立を避けることができ、訴訟まで発展せずに話し合いの段階で解決できる可能性もあります。
なお、使い込みの金額が少額であれば、調査にかかる手間や訴訟にかかる費用の方が大きくなり、あきらめたほうがいい場合もあります。
古山総合法律事務所では、親の通帳からの使い込みなど相続トラブルについてのサポートやアドバイスをおこなっています。
初回無料相談では、① ご事情やご希望をふまえた解決策のご提案、② 解決までの道すじ、③ 個別の質問への回答をおこないます。
あなたの気持ちに寄り添い、専門知識や解決ノウハウ、これまでの解決事例を交えながら対処法を分かりやすく丁寧にお話しいたします。
解決実績豊富な当事務所まで安心してご相談ください。
一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。