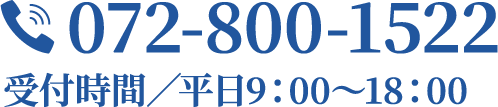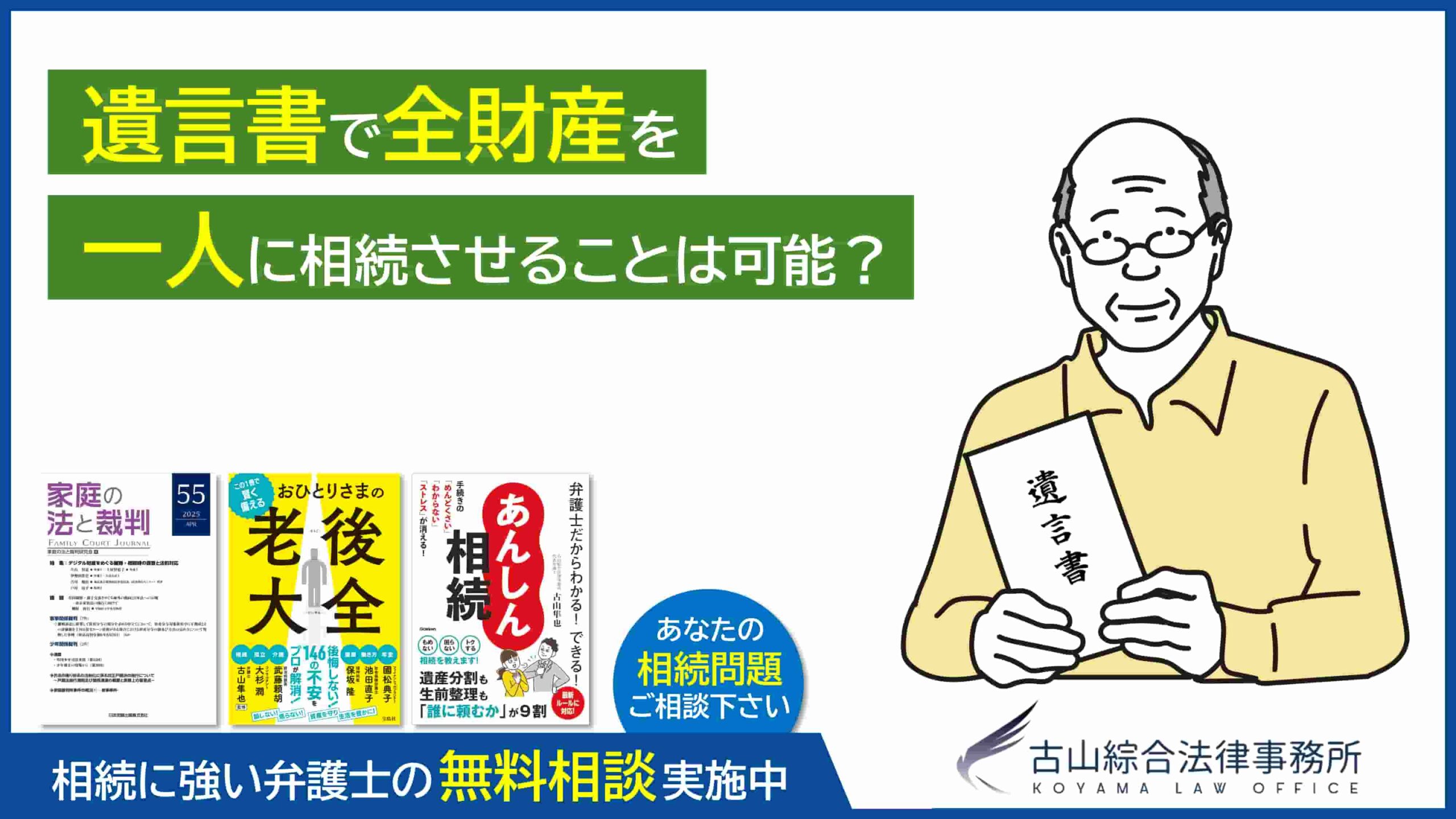遺言書で全財産を一人に相続させることは可能?
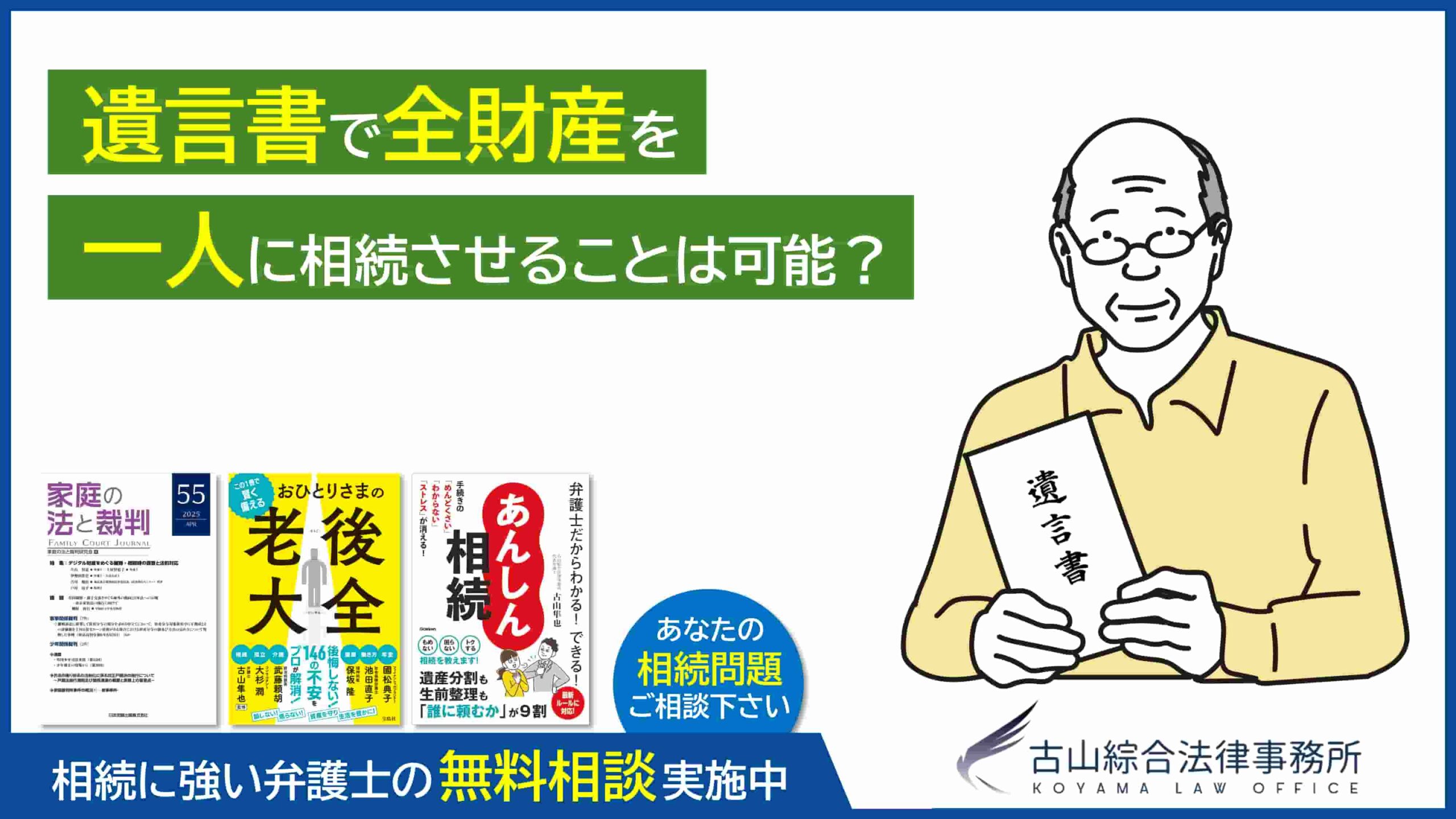
さまざまな家庭の事情や家族の関係性により、相続人が複数いる場合でも「1人の相続人に全財産を相続させたい」と考える人は少なくありません。
相続においては、「特定の相続人一人に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成することは可能です。
相続が発生した場合、遺言書に書かれた遺言者の意思が最優先されます。
しかし、実際に他の相続人に一切渡さずに一人の相続人が全財産を受け取ることができるかというと、主に「遺留分」の問題が立ちはだかります。
この記事では、一人の相続人に全財産を相続させる場合の遺言書の書き方やリスクと対処法について解説します。
また、相続する側として「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書があった場合の対処法についても解説します。
遺留分の問題点-法律で最低限保障された相続分
全財産を一人に相続させたいと思うなかで一番のハードルとして考えられるのは、他の相続人による遺留分の請求です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言者(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人(遺言者の配偶者、子供、両親・祖父母など)に対して法律上、最低限保障されている相続分です。
遺留分は遺族の生活保障のために定められた制度です。
被相続人の意思とは関係なく、遺留分の請求をおこなうことができ、被相続人の意思とは関係なく、遺留分の請求をおこなうことが可能です。
参照 民法第1043条(遺留分の帰属及びその割合)
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の12 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分権利者と遺留分の割合についてまとめると次の表のとおりです。
【遺留分権利者とその割合】
| 相続人の組み合わせ |
遺留分 |
各人の遺留分 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
配偶者 1/4、子 1/4 |
| 配偶者と直系尊属 |
1/2 |
配偶者 2/6、直系尊属 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし |
| 配偶者のみ |
1/2 |
配偶者 1/2 |
| 子のみ |
1/2 |
子 1/2 |
| 直系尊属のみ |
1/3 |
直系尊属 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ |
なし |
なし |
※子や直系尊属が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で均等に分けます。
遺言書の内容が「特定の相続人一人に全財産を相続させる」というものだった場合、他の相続人は、全財産を受け取った相続人または受遺者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを要求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
したがって、「特定の相続人一人に全財産を相続させる」という内容の遺言書の作成自体は可能ですが、他の相続人の遺留分を侵害していた場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、一人が全財産を承継することはできないことがあります。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、相続人となる予定の「推定相続人」である兄弟姉妹が複数人いる場合で、特定の兄弟姉妹に相続させたい場合は、遺言書に「【特定の兄弟姉妹】に相続させる」と書くようにします。
法律の改正により、遺留分侵害に対する被害回復の方法が「金銭賠償(お金を支払う)」のみとなりました。
遺留分は法律で定められた権利ですが、他の相続人が請求しなければ支払う必要はありません。
そのため、遺言者はあらかじめ他の相続人に対して「遺留分を請求しないでほしい」と遺言書に書いておくことは可能です。
遺留分の請求を強制的に止めることはできませんが、「遺言者の希望ならしかたがない」と納得してくれる可能性もあります。
1.【遺産を残す側】一人だけに全財産を相続させる方法
相続人が複数いる場合でも、一人に全財産を相続させたいケースとして次のような理由が考えられます。
・特に感謝している、思い入れのある相続人に全財産を相続させたい
例)事業を引き継いでくれる長男に全財産を相続させたい、子どもたちは自立しているが残された妻が心配なので全財産を相続させたい、介護してくれた次女に全財産を相続させたいなど
・他の相続人に遺産を渡したくない
例)看過できない暴力や非行がある、親子の確執など修復不可能な関係性の相続人には遺産を渡したくないなど
・相続人以外の人に遺産を残したい
例)介護してくれた長男の妻に感謝として全財産を渡したい、相続人間が不仲なため第三者に全額遺贈・寄付したい
・相続税の負担を減らすため
例)死後、配偶者も高齢であるため、二次相続などを踏まえて特定の相続人一人に相続させたいなど
このように、財産を一人に相続させたいといっても、その理由はさまざまです。
そもそも一人しか相続人がいない場合は、残された相続人に遺産が継承されるため、遺言書の作成は不要です。
問題となるのは、相続人が複数いる場合や相続人以外の第三者に遺産を残したい場合です。
一人だけに全財産を残したい場合、遺言書を作成する方法と生前贈与を活用する方法があります。
法務面や税務面の問題をと照らし合わせて、遺言書の作成と生前贈与の活用を組み合わせたり、養子縁組や生命保険などの他の相続対策と合わせることを検討することもできます。
相続対策はその人の財産状況や家族との関係性、希望する分割方法などによってベストが異なる、オーダーメイド性の高い問題です。
当事務所では、法務・税務面からの視点で生前贈与を活用して、希望に沿った相続を叶えるサポートもおこなっています。
生前贈与に関する問題も初回法律相談無料にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
1-1.一人に財産を相続させるための遺言書の作成方法
遺言書を書く前に、まずは自身の財産がどれだけあるかを調べて一覧にまとめます。
相続財産の評価方法は財産によってさまざまで、評価方法が間違えていると相続時に遺産分割を巡ってトラブルが生じる可能性があります。
預貯金以外に財産がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な財産評価や相続税納付の際の資金準備を含めた事前対応をおこなうことができます。
1-1-1.遺言書を書く際の注意点
一人だけに全財産を渡すとなると、遺留分の権利を持つ他の相続人を納得させるような遺言書を作成する必要があります。
遺言書には遺産分割方法に加えて、遺言書の書き手の想いをつづることも可能です。
これを「付言事項(ふげんじこう)」と言います。
付言事項には法的効力はありません。
しかし、以下の内容について書き記すことで、遺留分の請求をはじめとする相続トラブルを回避できる可能性があります。
ー どうしてその相続人に全財産を渡すのかを説明する
たとえば
「長年に渡って一人だけ献身的に自身の介護をしてくれたから」
「負債を含めた事業を全て引き継いでくれるから」
「子どもは既に自立しているから今後の生活のために妻に全財産を渡したい」
など、他の相続人が納得できるような理由を具体的に書くことで、想いが伝わる可能性があります。
ー 遺留分侵害への配慮をする
特定の相続人一人に全財産を相続させることの理由についての記載に加えて、他の相続人に自身の想いを尊重してもらえるようお願いするようなメッセージを書くことで納得してくれる可能性があります。
ただし、付言事項として「遺留分を請求しないようお願いします」と直接書いてしまうと、遺留分を請求できるということを知らなかった相続人が「遺留分の請求ってなんだろう」と存在を知り、逆に遺留分の請求を行うことにつながる可能性もあります。
また、生前に他の相続人に贈与や金銭的援助を行ったことがあればその旨を記載し、もう十分援助したのだから遺産相続はあきらめてくれるようお願いするのもひとつです。
1-1-2.遺言書の文例
具体的にどう記載すべきか、遺言書の文例は以下のとおりです。
一人の相続人に遺産をすべて渡したい場合の文例
1 遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、遺言者の長女○○□子(XX年XX月xx日生)に相続させる。
2 長年に渡って亡き妻、私と同居し、献身的に介護をおこなってくれた長女に感謝し、全財産を相続させることにしました。
次女には遺言者の生前に海外留学の費用と結婚した際に住宅の購入費用を援助したことから、長女に異議を述べることなく、これからも姉妹仲良く助け合ってくれることを望みます。よろしくお願いします。
遺言者の妻は既に他界し、相続人は長女と次女の2人、遺言者は長女と同居しながら介護してもらったことから、長女に全財産を相続させたいというケースにおける文例です。
1には「遺言者の財産を誰に何をどれだけ渡したいのか」を記載します。
2は付言事項です。
1だけでは相続させたくない次女から遺留分を主張されるリスクがあるので、長女に全財産を相続させることの理由について記載することで想いを尊重してもらえるように付言事項を添えます。
今回のケースでは、既に生前に次女には贈与や金銭的援助を行ったことを記載し、既に十分に義理を遺留分の請求を思いとどまってくれるような文章を添えています。
「遺留分の請求をしないようにお願いします」と直接的な表現にしてもかまいませんが、次女が相続の知識がなく、自分も遺留分の請求ができるということを知らなかった場合には、その一文を添えることで逆に遺留分の請求を誘発してしまう可能性があります。
また、財産を渡したくない相続人が勝手に遺言者の財産である金銭の引き出しを行うなどの行為があった場合には、その相続人の遺留分が主張することに備えて、以下のような付言事項を記載するといいでしょう。
(付言事項)
相続人Bに遺留分を払わなければならない場合、わたしが生前老後のために蓄えてきたC名義の3000万円の定期預金について、譲渡した覚えがないのに、令和〇年〇月〇日にBが無断で引き出したため、それを遺留分の算定に加えるものとする。
その人が主張する遺留分に相当する財産の取得が既にあったことを遺言書に書き残しておくことで、その相続人の遺留分の主張を弱めることができる可能性があります。
状況によっては、財産を相続させたくない相続人に対して相続放棄をしてほしいというお願いを記載することもできます。
相続放棄をした場合には、はじめから相続人でなかったことになるため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含む一切の財産を引き継ぐことはありません。
負債も含まれる事業承継を理由に全財産を一人に渡す場合は理解してもらえる可能性があります。
1-1-3.遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために、相続関連の手続きを行う人です。
遺言執行者は必ずしも指定しなければならないというものではありません。
しかし、もし遺言で遺言執行者を指定していなかった場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをしなければならなくなる可能性があります。
スムーズに相続をおこなうためにも、遺言の内容を実現するための遺産の管理など必要な行為をする権利と義務を持つ人を指定しておくほうが安全です。
遺言執行者には弁護士や司法書士など、法律の専門家を指定することができます。
相続は財産の内容や個別の事情によってベストな方法が異なる、オーダーメイド性の高い問題です。
そのため、相続トラブルを避けたい場合には、遺言書を作成するときから弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。
信頼できる弁護士を遺言執行者に指定することで、法的トラブルを防ぎ、希望どおりの相続の実現に向けてサポートが受けられます。
1-1-4.自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書の代表的な作成方法として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言はその名称のとおり、自分で遺言書を書いて作成するものです。
平成31年1月13日の法律改正により、自筆証書遺言の作成に関するルールが変更されました。
それまではすべて自筆による作成が求められていましたが、現在は財産目録に限りパソコンなどで作成することも可能になりました。
なお、施行日より前に法改正後に認められた形式で作成された自筆証書遺言書は、改正前の法律が適用されるため作成方式に反するため無効になります。
また、令和2年からは自筆証書遺言を法務局で保管・管理してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」も始まりました。
自筆証書遺言が自宅などで保管されていた場合は、遺言書の死亡後、保管者や発見者は家庭裁判所で「検認手続き」を受けなければなりません。
しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合は「検認手続き」は不要です。
検認手続きは、発見時の状態を確認・記録しておくことで、偽造・変造を防止するためのものです。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書は法務局で保管されるため、そのリスクはないとしていため検認が不要になります。
また、遺言書の紛失のおそれがなく、相続人などの利害関係者による遺言書の破棄や隠匿なども防ぐこともできます。
ただし、法務局に預けているといっても、遺言書の有効性まで保証してくれるわけではありません。
形式の不備や内容の問題に関しては自己責任となりますので、書き方にはくれぐれも注意を払う必要があります。
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言による作成のメリットは、元裁判官や元検察官といった法律の専門家である公証人が作成してくれるため、法的にも有効な信用性の高い遺言書です。
公正証書遺言は作成後、公証役場で保管されるため、紛失のおそれもなく、相続人などの利害関係者による遺言書の破棄や隠匿、改ざんなどの心配もありません。
自筆証書遺言での作成に不安がある場合は公正証書遺言での作成をおすすめします。
1-2.生前贈与の活用
遺言書を作成して遺産を渡す残すこともできますが、生前贈与で推定相続人などにあらかじめ財産を渡しておくこともひとつの方法です。
ただし、生前贈与をするには「法務面」と「税務面」で問題が発生する可能性があります。
法務面では、相続開始となった際に他の相続人から「一人だけ特別に金銭を受け取っていた」として特別受益を主張される可能性があります。
生前に結婚資金や住宅購入資金の援助など、特定の一人の相続人だけが特別に利益を受け取っていたにもかかわらず、そのまま遺産分割をおこなうと不公平が生じます。
そのため、他の相続人から特別受益を主張された相続人は、その金額分を考慮して遺産分割をおこなうことになります。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
一人だけに全財産を渡したいと思って対策したつもりの生前贈与が特別受益として主張されて、他の相続人にも財産が分配される可能性があるので注意が必要です。
税務面では、贈与税の問題があります。
贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類の非課税特例制度があります。
暦年贈与は1月1日から12月31日までの1年間に110万円以下なら贈与税がかからないとする制度です。
従前、亡くなる3年前以内の生前贈与は相続財産に含めることとされていました。
つまり相続財産の総額が増えるため、相続税に影響があります。
2024年の税法改正により、「3年以内」から「7年以内」となり、相続財産に含められる範囲が広くなりました。
「相続時精算課税制度」は、生前贈与にあたり2500万円までを非課税とするものです。
この制度も、2024年に改正がありました。
従前は、相続時に贈与された財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算するため、単なる税金の支払いの先延ばしでしかありませんでした。
しかし、税法改正により、2500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除、相続税計算時の足し戻しも不要となりました。
暦年贈与よりもメリットの大きくなった相続時精算課税制度ですが、60歳以上の祖父母・父母などの贈与者から、18歳以上の子や孫に対して生前贈与をした場合にしか選択できません。
このように、各種制度をよく検討したうえで非課税特例(「相続時精算課税制度」「配偶者控除の特例」「住宅取得等資金の非課税」など)の適用を受ける場合には、贈与税の申告期限までに申告をおこなう必要があります。
2019年の相続法改正から遺留分の計算時に基礎とされる特別受益の範囲が変わり、原則として、相続開始前から10年以内の贈与に限定されることになりました。
つまり、基本的には、10年を超える生前贈与により受けた特別受益があったとしても、遺産分割時に特別受益を主張できなくなります。
そのため、一人に全財産を相続させたいという想いを叶えるなら、早い段階から生前贈与を活用し、遺言書と組み合わせることで効果的な相続対策が望めます。
1-3.第三者に遺産を残す方法
遺言書で、事実婚(内縁)の相手や認知をしていない非嫡出子、お世話になった人や団体など、法定相続人以外の第三者に遺産を渡すことも可能です。
この場合は相続ではなく「遺贈」といい、遺言書に記載する場合も「遺贈する」という書き方になります。
遺贈と似て非なるものとして「死因贈与」もあります。
遺贈との大きな違いは、遺言書で一方的に財産を渡す意思表示をおこなう遺贈に対して、死因贈与はあらかじめ財産を渡す人ともらう人とで双方の合意(死因贈与契約)が必要です。
死因贈与は口頭でも契約成立するとされています。
財産を渡す人が死亡したときに効力が発揮される契約であるため、相続人とのトラブルが発生した時に贈与の立証がむずかしく、書面を残しておくことが重要です。
ただし、他に相続人がいるにもかかわらず第三者に全財産を遺贈や死因贈与するとなった場合も、やはり他の相続人の遺留分をなくすことはできないため、遺留分に配慮する必要があります。
遺言書には、付言事項として第三者に全財産を渡す必要があった理由や他の相続人には生前に既に十分な金銭援助を行ったなど、他の相続人を説得できるような内容を記載しておくと良いでしょう。
また、生前に相続人以外の第三者に贈与することもできます。
死亡前1年以内の生前贈与であれば、受贈者である第三者に対しても、遺留分権利者である相続人は遺留分を請求することができます。
ただ、原則として、それ以前にされた生前贈与に対してはでは遺留分の請求はできません。
早めに相続対策をする場合は生前贈与の活用も有効です。
このほか、生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産とされ、原則として遺産分割や遺留分の対象とならないので生命保険を活用する方法もありますし、養子縁組をすることで財産を渡すこともできます。
1-4.相続させたくない相続人がいる場合
「絶対に長男だけには財産を渡したくないから、全財産を次男に相続してもらいたい」というようなケースもあるでしょう。
単に不仲だからという理由では無理ですが、一定の条件を満たしていれば、相続権を持っている人(推定相続人)を相続から外す「相続廃除」という制度を利用することができます。
推定相続人に兄弟姉妹は含まれません。
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、相続廃除でなく遺言で対処できるからです。
被相続人(遺言者)本人が家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行い、裁判所が認めた場合、その推定相続人は相続権を失います。
参照 民法第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
以下のようなケースの場合、相続廃除の申し立てができます。
・推定相続人が被相続人に対して肉体的、精神的に虐待をおこなった
・推定相続人が被相続人に対して日常的に暴言を吐くなどの侮辱があった
・推定相続人が被相続人の財産を無断で取得したり処分していた
・推定相続人が抱えた多額の借金を被相続人が返済した
・推定相続人に著しい非行があり、有罪判決を受けている
相続廃除された推定相続人は相続権を失うので、遺留分を請求する権利も失います。
注意したいのは、相続権を失うのは廃除された当人のみで、もしその相続人に子どもや孫がいる場合は代襲相続として、その相続権は引き継がれます。
代襲相続とは、相続時点で相続人となるべき者が死亡、廃除、相続欠格などにより相続権がない場合、その子が代わって相続人となる制度です。
「長男に著しい非行があったから、長男を相続廃除して長男一家には財産を渡したくない」と思っても、長男の子どもに対しては相続廃除の申し立てはできません。
代襲相続もさせたくない場合は遺言書に付言事項として書き加えるか、別の方法を考える必要があります。
なお、後に猛省するなどして和解した場合には、相続廃除を取り消すこともできます。
1-4-1.「相続廃除」と「相続欠格」の違い
相続廃除と同様に相続権を失う制度に「相続欠格」があります。
相続欠格は、推定相続人が被相続人からの相続に関して不正や犯罪などをはたらいた場合、当然に相続権を失う制度です。
参照 民法第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格には裁判所での手続きは必要なく、民法891条に抵触する事実があれば相続権が剥奪されます。
| 制度 |
概要 |
代襲相続 |
| 相続欠格 |
法律で定められた特定の不正行為を行った場合に、自動的に相続権を失う制度。
被相続人(亡くなった方)の意思は関係ありません。 |
認められる |
| 相続廃除 |
被相続人に対して虐待や重大な侮辱などを行った相続人について、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きを経て相続権を剥奪する制度。 |
認められる |
ただし、相続欠格に該当するのは被相続人の相続問題に対して非常に重大な問題行動があったときのみなので、推定相続人を相続させたくないと考える時点で相続欠格を考慮に入れるのはむずかしいでしょう。
また、相続欠格の場合も相続廃除同様、代襲相続は認められていますので、相続欠格者に子どもや孫がいる場合には相続権は引き継がれます。
2.【相続人側】遺言内容を争う方法
遺言書に、自身の相続分がなかった相続人として、遺産を受け取る相手方と争う方法について解説します。
自身に不公平な遺言書が見つかったとき、その相続人が遺産分割や相続を求めるためには3つの方法があります。
2-1.遺言書の無効を争う
遺言書が無効になれば、遺言書はなかったものとして、相続人全員の遺産分割協議で相続割合を決めることになります。
遺言書が無効になるケースとして、① 法律で定めた形式に違反している、② 遺言能力に問題があることが挙げられます。
法律で定めた形式に違反しているケースとして、遺言書が自筆証書遺言の場合には、次のような点があります。
・遺言者の手書きではない
自筆証書遺言書は原則全文が自書でなければなりません。
ただ、例外として、平成31年1月13日以降に作成する場合、財産目録はパソコンなどで作成してもかまいません。
・日付がない、日付が特定できない形式で書かれている
遺言書作成日の記載は必須事項です。
作成日の記載がない、あるいは「XXXX年XX月」やや「XX年XX月 吉日」「XX月XX日」など、「年」「日」の記載のいずれかが欠けていて「いつ」書いたものなのか特定できなければ無効になります。
遺言書は新しく書き直すことが可能です。
前後の遺言書で、抵触する内容については、後日付の内容が優先されます。
そのため、日付の記載はとても重要です。
・遺言者の署名・押印がない
遺言者本人の署名と押印は必須事項です。
署名については戸籍上の氏名を記載するのが通常です。
俳句の俳名、俳号やニックネームやペンネームなどは、同一人物との証明が難しいため避けましょう。
押印は実印に限らず、認印や拇印でも良いとされています。
・訂正の方法を間違えている
遺言書は訂正の方法も法律で決められています(民法968条第3項)。
たとえば間違えた部分を修正ペンやテープを使っていたり、塗りつぶしていると、その修正した箇所が無効になる可能性があります。
参照条文 民法968条第3項(自筆証書遺言)
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
・遺言書が共同で書かれている
夫婦によくありがちですが、2人以上でひとつの遺言書を作成した場合は無効です。
共同遺言といいますが、法律で禁止されています(民法975条)。
また、遺言書の形式に不備がなくとも、遺言書作成時に被相続人が認知症などを患っていた場合、事理弁識能力(意思能力)がなかったとして遺言書の効力が無効になることがあります。
認知症であっても常に意思能力がないとは限らず、タイミングによって変動するケースもあるので、遺言書作成時点において意思能力があれば遺言は有効に成立します。
そのほか、遺言書作成時に詐欺、脅迫があった場合、遺言書偽造、改ざんがあった場合も無効となります。
遺言書の無効を主張する流れとしては、まずは相続人同士の話し合いで解決を模索します。
当事者同士での話し合いで解決ができない場合は、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。
無効とする争点は多くの場合、認知症などによる遺言能力の有無です。
遺言能力がなかったことを証明するために、被相続人が入通院していた病院や介護施設から診療記録や看護記録、介護記録を取り寄せ、判断能力の低下などを確認していく必要があります。
資料の収集や調査、分析など一般の方には難しい作業となるため、遺言無効を争う場合には弁護士に依頼することが多いです。
2-2.遺留分を請求する
遺言書が有効に成立している場合で、遺留分の侵害を受けている時には最低保障の相続分を請求します。
一見すると単純そうに思える遺留分侵害額請求ですが、現金や預貯金以外の土地や建物といった不動産、株式、骨董品、貴金属などの財産は評価が難しいケースがあります。
遺留分侵害額請求の期限には「時効」と「除斥期間」があります。
相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分を請求しなければ時効により、請求権が消滅します。
また、相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分を請求できなくなります。
この期間を「除斥期間」と言います。
2-3.特別受益(生前贈与)を主張する
特別受益とは、一部の相続人だけが相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。
遺産分割の際に、特別受益を含めて考えることで、公平な相続をおこなうことができます。
法律(民法903条)において定められています。
たとえば6,000万円の父の財産を相続する際に、長男だけが2,000万円の生前贈与を受けていたにもかかわらず、法定相続分どおりに遺産分割すると他の兄弟姉妹からすると不満に感じるでしょう。
このように不公平をなくすために、特別受益分を遺産に戻して相続分を計算しなおすことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
なお、生前贈与のすべてが特別受益にあたるわけではありません。贈与のうち「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」が特別受益にあたります。
また、前述した通り遺留分は民法第1043条に「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と規定されているので、贈与である特別受益も当然含まれます。
遺留分侵害額請求においての特別受益は原則相続発生前10年間以内に行われたものが対象となります。
特別受益に該当する生前贈与があったかどうかは、実際には被相続人の預金口座の入出金履歴を取り寄せして、不審な履歴がないかを確認することが必要です。
遺言書の有効性について争うにせよ、遺留分侵害額請求をおこなうにせよ、自分の相続額を増やすためには財産を調査することが大切なポイントです。
財産調査に関しても弁護士によるサポートがあれば、スムーズかつ正確におこなうことができます。
相続手続きには期限や時効、除斥期間が設けられているものが多く含まれます。
自身に不利な遺言書が見つかり、相続分をしっかり確保したいと思ったら、早い段階で弁護士にご相談ください。
3.まとめ
一人に全財産をわたすという内容で遺言書を作成できるものの、全財産を受け取ることになった相続人は他の相続人から遺留分を請求されたり、特別受益を主張されるなど、相続人間トラブルに巻き込まれるリスクがあるということを解説しました。
全財産を1人に相続させたいと考えるならば、あらかじめリスクを想定し、相続人同士で争いが生まれないよう配慮した相続対策を考えましょう。
当事務所では、法的リスクに備えた遺言作成から遺言執行者、遺産分割協議書の作成、相続人間のトラブルなど、相続問題を幅広く取り扱っています。
初回無料相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。